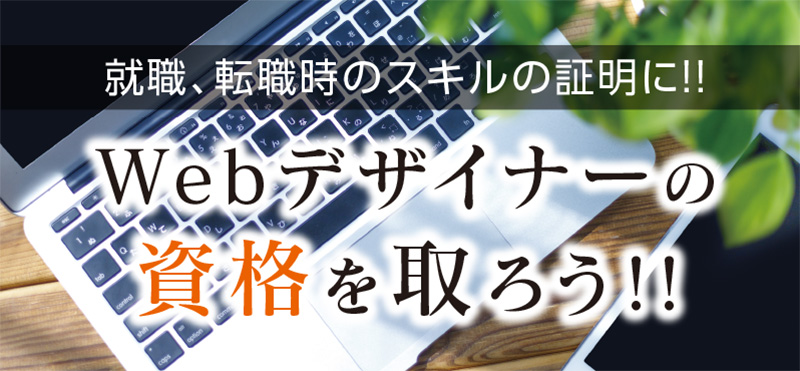【学習効率UP】ウェブデザイン技能検定3級試験(令和元年度第3回)の過去問題を徹底解説!!
過去問題の解説(令和元年度第3回学科試験)
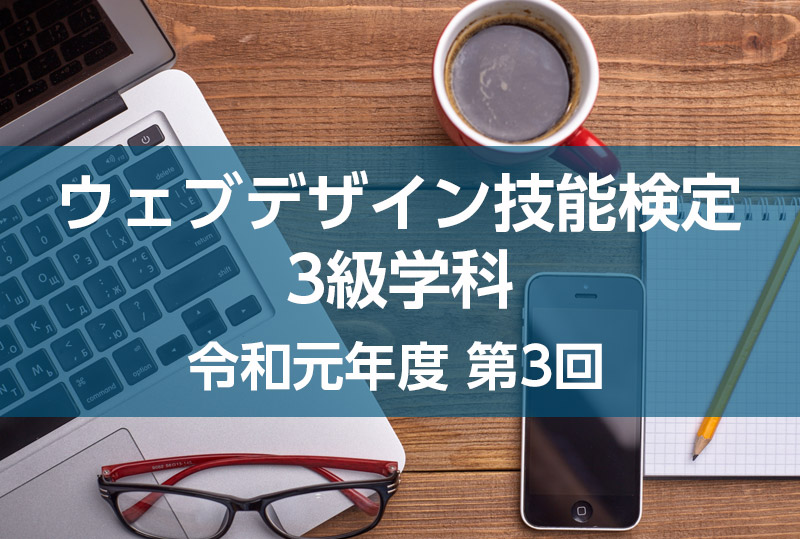 ※各設問において、正しものは○を、間違っているものは✖を選択してください。
第1問
HTML5ではDOCTYPE宣言は省略できる。
※各設問において、正しものは○を、間違っているものは✖を選択してください。
第1問
HTML5ではDOCTYPE宣言は省略できる。
答え=× HTML5では最初に<!doctype html>と宣言を記述することで、ブラウザはその文書がHTML5で書かれたものと認識しますので、この宣言は必須です。以前はこの宣言自体をすごく長々と書いたものですが、現在は短く一文入れるだけで良くなっています。
第2問 PNG形式は256色表示用の画像フォーマットである。
答え=× PNG形式は256色の保存形式もありますが(PNG8)、JPEGと同じように1670万色の保存形式のものもあります(PNG24)。
第3問 CSSで色やフォントを指定した場合には、すべてのデバイスやユーザ環境で、それらは同一に表示される。
答え=×
まずフォントですが、ユーザーの端末の環境でデバイスフォントにバラつきがあります。Winではデフォルトだと「メイリオ」や「MS Pゴシック」、Macだと「ヒラギノ角ゴ」がポピュラーです。色も256色中216色はどの環境でも統一されていますが、残りの40色はOS間でバラつきがあります。
ちなみに、このフォントをどの環境でも同じにしたい際は、WEBフォントを読み込んで指定してあげると、環境が違っても統一することができます。
第4問 VDT作業におけるディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすることが望ましい。
答え=○ もし周囲との明るさの差が大きかったら、作業がやりにくくて大変ですね。映画館で上映中にパソコンで仕事なんかしてたら大変です。
第5問 サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念及び国の責務、戦略、基本的施策等を規定している。
答え=○
サイバーセキュリティ基本法は、平成26年に成立した新しい法律です。ざっくりいうと問題文のとおりです。興味がある方は下記にて詳細をご確認ください。
もっと詳しく見る>>
第6問 著作物が著作権による保護を受けるためには所定の手続きが必要である。
答え=× 著作権は手続きなどは必要なく、またそのことについての明記がなくても自然に発生します。ネットで配布されているフリー素材などは、フリーと書かれてはいますが、商用はNGなど利用内容によっては著作権が発生するものも多々ありますので、使用の際は注意が必要です。
第7問 HTML5においても、i要素はテキストをイタリック体で表示させるための要素である。
答え=×
以前はi要素はテキストをイタリック体(斜体)で表す際のタグでしたが、HTML5からは仕様が変更されています。
HTML5でのi要素は「通常の文章とは異なる文章」を表し、例えば文章の中で心の声を表現する際や、専門用語を使用する際に、このi要素で囲みます。
第8問 文字色と背景色のコントラストがアクセシビリティに影響を与えることはない。
答え=× 文字色と背景色のコントラストが低いと文字が読みにくくなる(白の背景に白の文字をのせても見えないですよね)ので、できるだけ差をはっきりさせたほうが閲覧者は見やすくなります。
第9問 SVG形式の画像は、拡大や縮小をしても画質は劣化しない。
答え=○
SVG形式では画像を拡大縮小しても劣化しませんし、ファイルサイズも変わりません。グラフィックソフトのイラストレーターを使っている方はイメージしやすいかと思います。
PNGやJPEGは画像のサイズが大きいとそれに比例してデータのサイズも重くなりますが、SVGはベクターデータとなりますので、拡大してもサイズは軽いままで、かつ画質もきれいです。
使いどころとしては、完全な図版や装飾文字、イラストなど、ビットマップ画像が含まれていないものが適しています。私もサイト制作でよく使用してます。
第10問 ユニバーサルデザインとは、多言語対応のことのみをいう。
答え=×
ユニバーサルデザインとは、その対象者が日本人や外国人ということではなく、全ての人にとって使いやすく設計されたものですので、多言語対応のことのみということではありません。
また、こちらはWEBサイトに限ってのものではなく、日用品から施設など、身の周りのもの全てが対象となります。
WEBクリエイター転職情報はこちら ※以下の設問に答えよ。 第11問 次のHTMLコードが示すことがらに当てはまるものを、以下より1つ選択しなさい。
HTML
<link rel="icon" href="images/nspc.ico">
- サイト内共通の外部スタイルシートを示す
- サイト内共通のロゴマークを示す
- ファビコンの指定を示す
- ブックマークの指定を示す
答え=3
ファビコンとは、そのホームページのロゴアイコンのことで、みなさんもブラウザのお気に入りに登録した際に、サイト名の左横に小さなアイコンが表示されているのを見ていると思いますが、あれがファビコンです。
HTMLにファビコンを設置する際は、上記のようなコードを挿入します。特長は画像の拡張子が「.ico」となっていますので、この拡張子の画像があったら、それはファビコンと認識して大丈夫です。
WEBページにファビコンを設置する際は、ネット上にファビコンを作成するサイトがたくさんありますので、そちらを利用すると良いです。
第12問 ビデオ上に次の例のような操作インタフェースを表示したい。このとき●●に記述すべき属性はどれか。以下より1つ選択しなさい。
HTML
<video ●● width="250">
<source src="sample.mp4" type="video/webm">
</video>
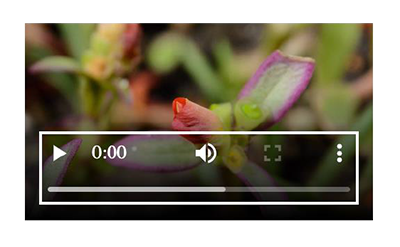
- controls
- interface
- video-nav
- video-ui
答え=1 操作インタフェースを表示したい際は「controls」と記述します。controls属性を指定すると、再生、一時停止、再生位置の移動、ボリュームなど、動画を使いやすくする操作画面をブラウザが自動で表示してくれます。
第13問 16進数であらわした色の値のうち、redと同じ色になるものはどれか。以下より1つ選択しなさい。
- #000000
- #ff0000
- #00ff00
- #0000ff
答え=2
16進数で色を表現する際、左から2ケタずつの数字を1グループとしてRGBで表します。問題ではred(赤)はどれか?ですので、この場合は一番左の2ケタの数字「R(レッド)」がff(最大値)となっていないといけません。
16進数では0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→a→b→c→d→e→fで色を表します。fが最大値となりますので、一番左の2ケタの数字がffで赤が最大、中央の2ケタ「G(グリーン)」が00で最小、右の2ケタ「B(ブルー)」が00で最小で「#ff0000」は赤となります。
では、この考え方で問題の他の数字が表している色を読み解くと、1はすべてが最小の0なので黒、3は中央の2ケタがffでそれ以外が00なので緑、4は右の2ケタがffでそれ以外が00なので青となります。
第14問 CSSで子セレクタの指定がされているものを、以下より1つ選択しなさい。
- ul li{color: #ffffff;}
- ul , li{color: #ffffff;}
- ul > li{color: #ffffff;}
- ul * {color: #ffffff;}
答え=3
セレクタを > で区切ると、セレクタの直下の階層にある子セレクタを対象にスタイルを適用することができます。
この指定方法の良い点は、子セレクタだけが対象で、孫以下は設定が反映されない点です。
問題ではul直下のli要素に対して文字色を白と設定していますが、入れ後でさらにli要素があった際、普通に書くとそれも白になってしまいます。それぞれで任意でクラス名を付ける分ける方法もありますが、できるだけHTMLはスマートに記述したほうが良いので、無駄に書き込むよりはこういう書き方をしたほうが、後々修正する際も見やすくて作業がしやすくなります。
第15問 ウェブサイトに大量のリクエストや巨大なデータを送りつけることで、サーバをダウンさせる攻撃手法はどれか。以下より1つ選択しなさい。
- パスワードリスト攻撃
- クロスサイトスクリプティング
- DoS攻撃
- ドライブバイダウンロード
答え=3
巨大なデータを送りつけて、サーバーをダウンさせる攻撃手法を「DoS攻撃」といいます。これの特長は個人が自分のパソコンから一人で攻撃をおこなうことです。これの発展形で「DDoS攻撃」というものがありますが、こちらは複数人でサーバーをダウンさせる攻撃方法です。
今回はDoS攻撃についてでしたが、これまでのパターンから上記4択の攻撃手法はすべておぼえておいたほうが良いです。以下に簡単に記載しておきますので、できるだけおぼえておいてください。
▼パスワードリスト攻撃
悪意を持つ第三者が、何らかの手法によって入手したID・パスワードのリストを利用してWebサイトにアクセスを試み、利用者のアカウントで不正にログインされてしまう攻撃のこと。
▼クロスサイトスクリプティング
攻撃対象のウェブサイトに、セキュリティが弱い掲示板のようなウェブアプリケーションが掲載されている場合に、第三者がそこへ悪意のあるプログラムを仕掛けて、サイト訪問者の個人情報を盗むなどの被害をもたらす攻撃のこと。
▼ドライブバイダウンロード
悪意のあるサイトを訪問した際、閲覧者の意思に関係なく自動的にウイルスなどの不正なプログラムをダウンロードさせる攻撃のこと。
第16問 HTMLで段落を表現する場合の正しいマークアップ方法はどれか。最も適切なものを以下より1つ選択しなさい。
- p要素のタグで囲む
- div要素のタグで囲む
- br要素を使って前後を1行分ずつあける
- margin要素を使って前後を1行分ずつあける
答え=1 HTMLで段落を表現する場合は、その対象を「p要素」で囲みます。コーディングではとくに使用頻度が高い要素です。
第17問 次に示したのは、ウェブコンテンツJIS(JISX8341-3)のガイドライン1.1である。●●にあてはまる語句として、最も適切なものを以下より1つ選択しなさい。
1.1●●のガイドライン
全ての非テキストコンテンツには、拡大印刷、点字、音声、シンボル、平易な言葉などの利用者が必要とする形式に変換できるように、●●を提供する。
- 文書構造
- 支援技術
- 変換アプリ
- 代替テキスト
答え=4 こちらは問い方をあえて難しくしているだけで、全ての非テキストコンテンツとは文字以外のものを指し、おもには画像などのことです。WEBページでは画像などを表示できない環境でアクセスしてきた人のために、通常は表示されませんが「代替テキスト」を入れるようにとなっています(alt属性)。制作者はより親切な作り方をしないといけませんよということですね。
第18問 HTMLコードでinput要素のtype属性に用いることのできない値を、以下から1つ選択しなさい。
- radiobutton
- checkbox
- text
答え=1
input要素はHTMLでフォームを作る際に使用します。input要素はHTMLのバージョンが上がるのと比例して、使える種類も増えていまして、最近では以前と比べて簡単に凝ったフォームが作れるようになりました。
ちなみに回答のradiobuttonはtype属性ではなく「checked属性」になります。
第19問 次に示したのは、ウェブコンテンツJIS(JISX8341-3)の達成基準1.4.1である。●●にあてはまる語句として、最も適切なものを以下より1つ選択しなさい。
1.4.1 ●●の使用の達成基準
●●が、情報を伝える、動作を示す、反応を促す、又は視覚的な要素を判別するための唯一の視覚的手段になっていない(レベルA)。
- 色
- グラフ
- ラベル
- テキスト
答え=1
JISX8341-3とは、サイトの閲覧者が見やすい、使いやすいサイトを設計するための制作者向けのガイドラインです。ちなみに8341は(や・さ・し・い)のゴロ合わせです。
問題文は「色」についてのガイドラインで、こちらは丸暗記で良いです。
第20問 CSSにおいて、親要素と同じプロパティの値を継承させる際に指定する値はどれか。以下より1つ選択しなさい。
- auto
- invert
- inherit
- override
答え=3
inherit(インヘリット)値は、親要素の設定を強制的に継承させたい時に使用します。実務でコーディングをしている人でも、inherit値はあまり使うことがないので、意識したことがない方も多いのではと思います。
CSSでは、親要素の設定を継承したほうが便利に作業できるものは、最初から自動的に継承されるようになっていますので、通常はinherit値は気にしなくても支障はありません。ただ、デフォルトでは継承されない要素を継承させたい時は、このinheritの存在を知らないと、同じ設定を何度も書かないといけなく、それはそれで作業も管理も大変になりますので、CSSのデフォルトでは設定を継承しない要素を、強制的に継承させたい時はinheritを使うとおぼえておけば良いと思います。
第21問 HTTPS通信の標準ポートを、以下より1つ選択しなさい。
- 22
- 80
- 110
- 443
答え=4
これはまたマニアックな問題が来たなという印象です。通信のポート番号はサーバー管理者などでない限りは、通常は知らなくて当然です。現役のWEBデザイナーやコーダーの方も知らないという方が多いのではと思います。試験ではこちらの正解率は低かったんじゃないかなぁと思います。
では解説に入りますが、インターネット上の通信ではそれぞれでポート番号が割り当てられています。通常WEBサイトにアクセスするとURLが表示されますが、本当はここには表示されていないだけで、見えない番号があります。HTTPなら80番、FTP(サーバーへのファイル)転送なら21番など。これらの番号は世界共通で割り当てられていて、これらを総称で「ウェルノウンポート」といいます。
ここではそれぞれのポートがどういうものかという解説までは割愛しますが、以下に代表的なものを記載していますので、試験対策としておぼえておいてください。
・HTTP→80番 ・FTP→21番 ・SMTP→25番 ・DNS→53番
・POP3→110番 ・HTTPS→443番
第22問 斜体で表示されている要素を正体(斜体ではない標準状態)に戻すCSSの表示指定はどれか。以下より1つ選択しなさい。
- font-style: none;
- font-style: auto;
- font-style: normal;
- font-style: straight;
答え=3
文字に対して何かしら設定をしている際、それをデフォルトに戻したい時は「normal」と記述します。
例えばあるブロック対して、文字の装飾を共通設定として親とした際、その中にある一ヶ所だけはその設定を反映させたくないという場合に、その箇所に対して「font-style: normal;」を設定することで、そこだけは標準の状態に戻すことができます。
第23問 HTML5の要素ではないものはどれか。以下より1つ選択しなさい。
- audio
- video
- movie
- picture
答え=3 HTMLに動画を埋め込みたい際はmovieとは書かず<video>~</video>でその内容を囲みます。音声なら「audio」画像なら「picture」です。
第24問 インターネットスキル認定普及協会のサイトで、ロゴ画像を表示させるために用いるimg要素の使用方法として最も適切なものはどれか。以下より1つ選択しなさい。
- <img src="logo.png">
- <img src="logo.png" alt="logo">
- <img src="logo.png" alt="ロゴ画像">
- <img src="logo.png" alt="インターネットスキル認定普及協会">
答え=4 こちらはalt属性に入れる文字を適切に判断できるかを問う問題ですね。alt属性とは画像が表示されない方に、代わりに文字でその画像が何なのかを伝えるためのものですので、ここに入れるテキストは漠然としたものではなく、閲覧者に正しく情報が伝わる文章を記述する必要があります。
第25問 body要素には、次のようなHTMLコードで要素inputtype="checkbox"とlabelが加えられている。このlabel要素のテキストがクリックされたときも、チェックボックスのオン/オフを切り替えられるようにしたい。その場合、label要素の●●に定めるべき属性はどれか。以下より1つ選択しなさい。
HTML
<input type="checkbox" id="item01">
<label ●●="item01">項目01</label>
- for
- target
- link
- to
答え=1 問題はフォームを作成する際のコードです。label ●●の●●にはforと記述します。これが他の単語に変わることはなく、HTMLの文法ですのでそのままおぼえてください。
WEBクリエイター転職情報はこちら 目次へ戻る